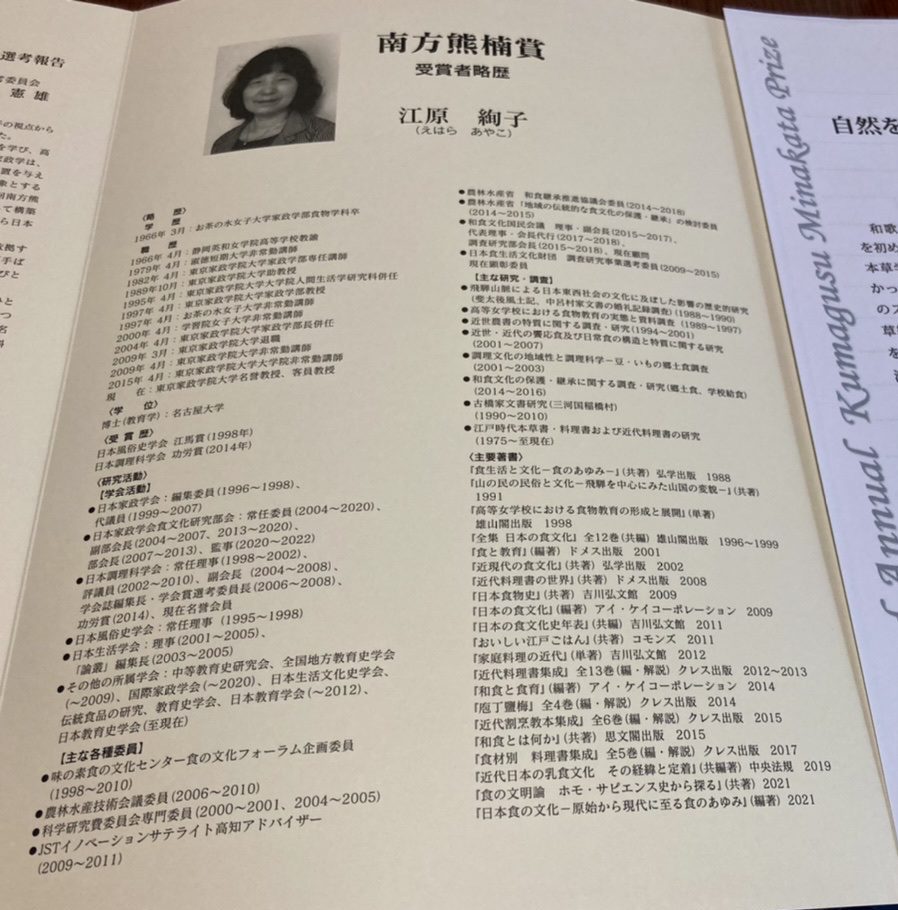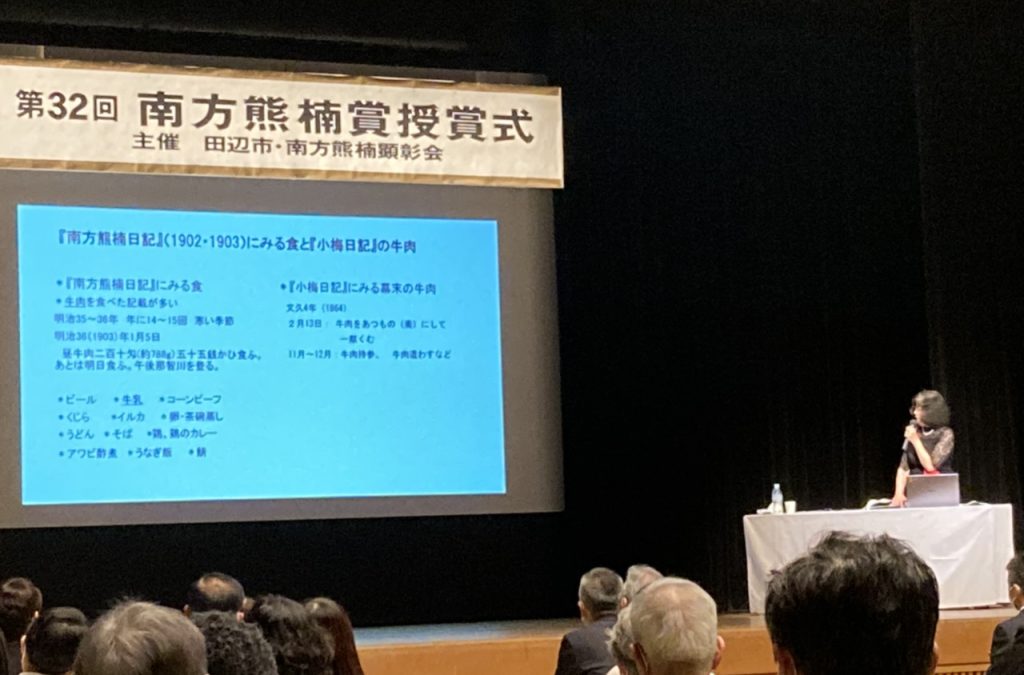先日、ギンリョウソウを見かけました。
ツツジ科の無葉緑植物。全体白く、葉緑素を持たずに菌類に寄生して生きる植物です。このような植物は昔は腐生植物と呼ばれ、今では菌従属栄養植物と呼ばれます。
ギンリョウソウについて書かれた南方熊楠の文章がありますので、そちらから引用します。
本草家の説に、支那書『物理小識』に載せた水晶蘭すなわちこれで、邦名はギンリョウソウ、ユウレイソウ、ユウレイタケ。それから『斐太後風土記』には、花葉茎共に純白、その光沢氷のごとくなれば氷草と呼ぶ、盛夏盆栽にして賞翫すべし、されど数日は保ち難しとある。学名モノトロパ・ユニフロラで、欧州、米国にも産し、植物解剖の初歩を学ぶに胚珠等の顕微鏡試験をするにしばしば用いられる。
南方熊楠「周参見から贈られた植物について」

光合成をやめて他の生き物に寄生して生きる植物を、熊楠は森の豊かさの象徴するものだと考えました。光合成をやめた植物の中には他の植物に寄生するものもいれば、土のなかの菌類に寄生するものもいますが、とりわけ熊野の森の豊かさを示すのが菌類に寄生する植物です。菌類に寄生する植物で、わりとよく見かけるのがギンリョウソウです。
この水晶蘭科の一類は、花実等の構造から案ずると、もと石南科に近いイチヤクソウ族のものが変成したらしく、その変成の主なる源因は、その生活の方法にある。すなわちもと葉緑素を具えた緑色の葉が日光に触れて空気から炭酸を取り自活しおった奴が、腐土(フムス)とて木や落葉が腐って土になりかかった中に生じ、いわゆる腐生生活を営むに至ったから、自活に必要な葉緑素を要せず、葉は緑色を失うて鱗片に萎縮退化し了(しま)うたのだ。その根を顕微鏡で見ると、微細な菌類と連合しおり、その菌類が腐土から滋養分を取って水晶蘭を養うのだ。
前同
熊楠は森におけるフムスの重要性をとくに訴えていました。フムスを熊楠は腐敗土とか腐土、腐葉土と訳していますが、今は腐植土と訳されます。動物の遺骸や植物の落ち葉などが腐ってできた土です。
フムス(腐植土)には菌根菌が菌糸を張り巡らせています。菌根菌は植物の根っこと共生して植物にリン酸や窒素を供給する菌類です。地上の植物の8~9割が菌根菌と共生していると考えられています。
豊かな森には、土の中に極めて多様で豊かな菌類の菌糸のネットワークがあり、土壌中に多様な微生物の世界があります。土の中の生物の多様性が、地上の生物の多様性をもたらします。
熊楠は目につかない土の中の菌類の豊かさこそが大切なのだということを訴えていました。
リンク