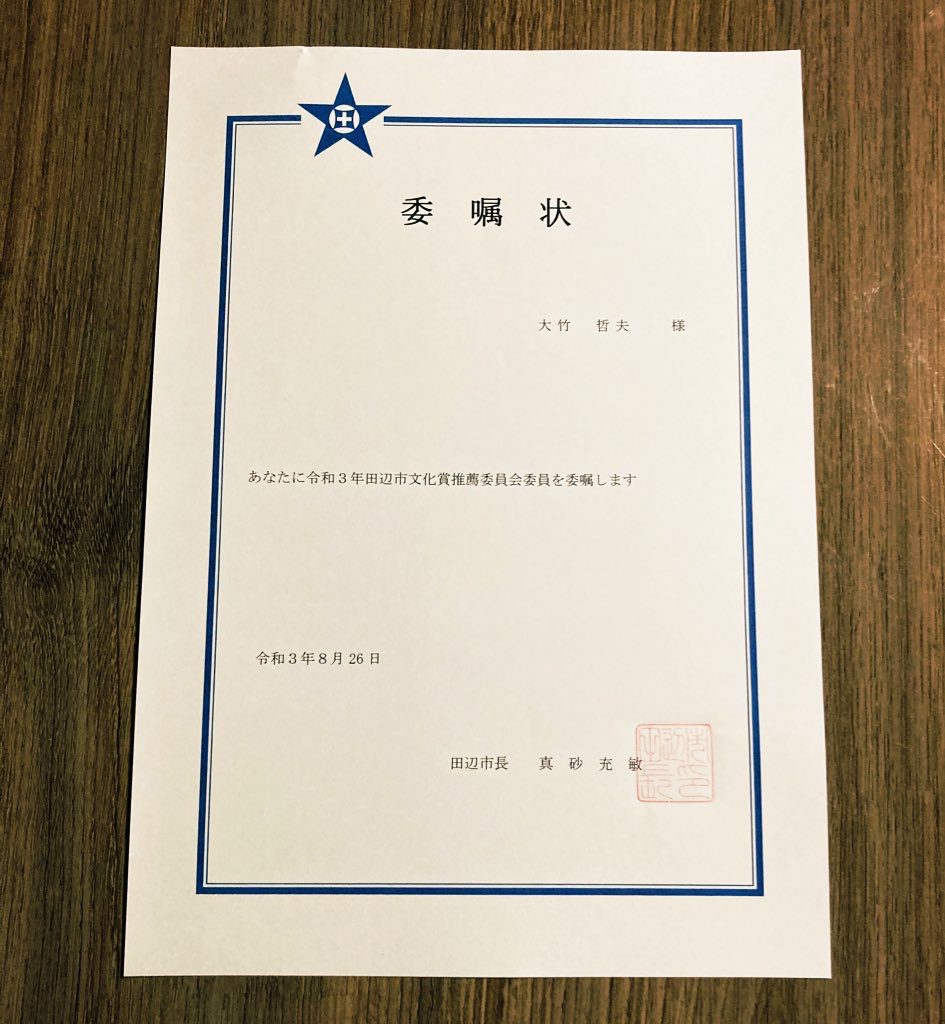白河法皇が院政を行なっていた1128年に書かれた記録(1535年書写「本宮文書第三号」)によると、熊野本宮大社の領地の面積は3,570町。
これは計算してみると東京ドーム907個分。
古代から中世後期にかけての1町の面積は約109メートル四方で、約11,881平方メートル。したがって3,570町は約42,415,170平方メートル。
東京ドームの面積が46,755平方メートルなので割ると907.17…。当時の熊野本宮大社の領地の面積はおよそ東京ドーム907個分に相当するのです。
しかもその領地のなかには476もの寺がありました。
今の熊野本宮大社とは全然スケールが違います。
上皇が熱心に通われた院政時代の熊野本宮は本当にすごかったのだと改めて思い知らされます。
リンク